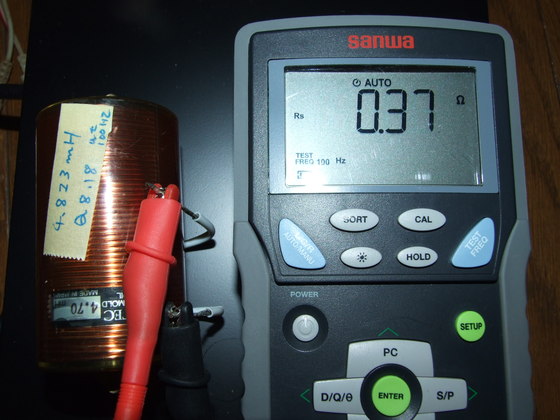マルチアンプ派なのにフルレンジとDF③
- 2017/10/22
- 22:00
マルチアンプ派なのにフルレンジとDFの続きです。 (最終回)
大げさですが驚愕の事実!
まとめです。
結局DFは、スピーカーとの相性と聴く人との相性の問題です。
スペックに記載されないこともあるDFですが、高すぎても小さすぎても良くありません。高いからと抵抗を入れれば極端に下がります。
前回ウーハー直接の場合のアンプオン時の制動に付いて書きましたが、下記写真のネットワーク入りのスピーカー例は、あまり制動が掛かるとは感じません。おそらくネットワークが影響しているのでしょう。
それでは最後に計算です。
DFの違いによるアンプの内部抵抗(8Ω負荷)
DF アンプの内部抵抗
1000 0.008Ω(8mΩ) (最新高級アンプ)
300 0.026Ω(26mΩ) (少し前の高級アンプ)
100 0.08Ω(80mΩ) (普通のトランジスタアンプ)
30 0.26Ω (無帰還アンプなど)
10 0.8Ω (出来の良い真空管アンプ)
1 1Ω (アマチュアの真空管アンプ)
DF=スピーカーのインピーダンス÷アンプの内部抵抗です。
ケーブルの影響
単純にスピーカーコード(ケーブル)の実測抵抗値0.2Ωを加算します。
DF1000のアンプは8÷(0.008+0.2)≒38
DF100のアンプは8÷(0.08+0.2)≒29
DF30のアンプは8÷(0.26+0.26)≒17
DF10のアンプは8÷(0.8+0.2)≒8
DF1のアンプは8÷(8+0.2)≒1
PAでパワーアンプがスピーカーの近くにあることが、ご理解いただけますね。
ですからいくらDFの高いアンプでも電線が長くなれば制動できなくなります。
追記
高いDFになる程に、微妙な抵抗値で影響を受けることがわかります。
別の観点から説明します。
DF300のアンプの出力保護回路リレーが0.020Ω(20mΩ)あったとします。
この保護回路リレーの代わりにMOSFETの1mΩ以下の電子スイッチにしたとします。これで一気にDF1000が実現できる訳です。
あまり大きなDFになると電流流入用のアンプの関係で測定も難しくなります。
この辺になると電線でショートした時に何Ωになるかわからないと理解はしにくいです。
デジタルテスターで赤黒ショートしたとき何Ωと出るかやってみてください。
下の写真は前回8mのスピーカー専用コードの電線を測った値です。
往復なので≒0.2Ωとします。
ミリΩ計が無いとこの説明は出来ませんでした。
ですからこんなコイルの入ったネットワークならどうなるか計算してください。
恐ろしいですよ。こうなるとマルチアンプは有効な方法です。
ちなみに上記DF1000に0.37を足すとDFは、僅か13になってしまいます。
DFとSPの相性で好みの音を見つけましょう!
電線で音が変わる!
おしまいです。